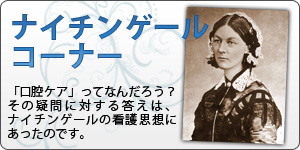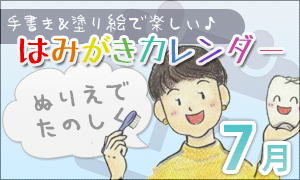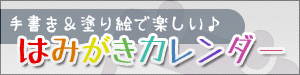さあー、歌いましょう!
皆さんおなじみの、お口の「パ・タ・カ・ラ・体操」は、食べる機能回復のリハビリの一つです。食前体操として取り入れている施設も多いと思います。「パ」「タ」「カ」「ラ」を発音することが、食べるために必要なお口の周りの筋肉や舌の筋肉のトレーニングになるのです。
では、簡単に各発音の説明をします。
「パ」:唇をしっかり閉じてから発音します。
複数の表情筋、口輪筋や頬筋を鍛え、食べ物の取り込みや食べこぼしを防ぐ
トレーニ ングです。
「タ」:舌を上あごにくっつけて発音します。
舌の筋肉を鍛えて食塊形成や食べ物を喉の奥まで動かすトレーニングです。
「カ」:喉の奥を閉じて発音します。
口蓋帆挙上筋を鍛え、食べ物を飲みこむ時に間違えて肺に入らないように喉の奥を
閉じるレーニングです。誤嚥予防の体操です。
「ラ」:舌を丸めて舌の先を上あごの前歯の裏につけて発音します。
「タ」同様に舌筋を鍛えて、食塊形成や食べ物の咽頭への輸送向上のトレーニングです。
10回ずつ発音し、5セット繰り返しましょう。唾液分泌も促されます。
食べるためには、呼吸のコントロールや、リズムも関係しますので、
「パ」「タ」「カ」「ラ」を発音する歌も有効だと考え取り組んでいます。
「パ」:すずめの学校 ちーちーぱっぱちーぱっぱ 雀の学校の・・・
「た」「ら」:うさぎのダンス ソソラソラソラうさぎのダンス、タラッタ・・・
「か」:七つの子 カラスなぜ鳴くのカラスは山に かわいい・・・
ただ歌うのではなく「パ」「タ」「カ」「ラ」の音のときには手をたたいて、その発音意識します。すると、はっきり大きい声で発声できます。
こうしてみると、子どもが童謡を歌うのは上手に食べるための発達に大切だったのだと、考えられます。昔の大家族ではおじいさんやおばあさんが孫の子守をしていましたが、そのとき孫と一緒に歌うことが自分自身のフレイルや認知症の予防に一役買っていたのと考えられます。
こんな風に実施していた【歌う口腔機能向上訓練】では、隣に座っている利用者さんも一緒に歌い始めたりします。そこで、歌いたい皆さんもお誘いしています。
いま行っているスタイルを紹介します。
- 歌謡曲や演歌、唱歌、童謡を織り交ぜる。
- 1番のみを歌う(例外もあります)
- 大きな字の歌集を作る。
- カラオケやCDは使わない。(音程など気にしない為)
5、体を使うレクレーションを組入れる
・「茶摘み」の手拍子のところは机をたたく
・曲によっては運動をしながら歌う
・「幸せなら手をたたこう」は万歳など様々な
運動や、唾液腺マッサージなどを取り入れる
★近づきすぎない、向かい合わないなど感染予防の配慮も必要。


約20曲を30分かけて歌うのですが、100歳近い方もしっかり口を開き歌ってくれます。「声が出んから歌は遠慮したい」と言っていたが、歌い終わった後に大きな声で「楽しかったけん、また誘てな」と言ったりします。歌と会話では脳が関わる領域が異なりますから、上手くしゃべれなくとも歌える方もいます。私が帰るころ別の部屋から、ケアで歌った歌を口ずさむ声が聞こえてくるのです。旧石器時代、言葉を使う前から人は歌っていたと言われている事からも、人間には歌うという欲求が根源的にある気がします。もちろん、お嫌な方もいるので無理強いはしません。
口腔ケアで訪問している特別養護老人ホームも、新型コロナウイルス感染の影響で、厳戒態勢が続いています。事態が長引くにつれて利用者さんの心にも変化が出てきているようです。仕方がないとわかっていても「娘に会いたい」「外出したい」など訴えがあります。叶わぬ期間が長くなると、心が疲弊し黙ってしまう方もいます。そんな利用者さんのこころを、歌はひと時でも癒してくれている気がします。歯科衛生士の【口腔機能向上訓練】でなくとも、歌うことすべて【口腔機能向上訓練】になっています。
利用者さんのために、そしてご自身のために、さあー、一緒に歌いましょう!







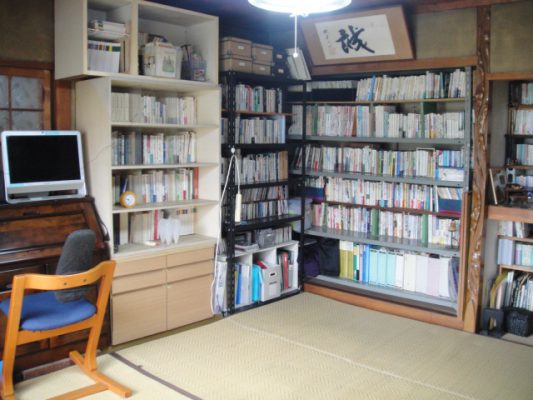





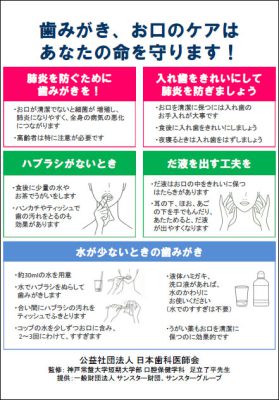



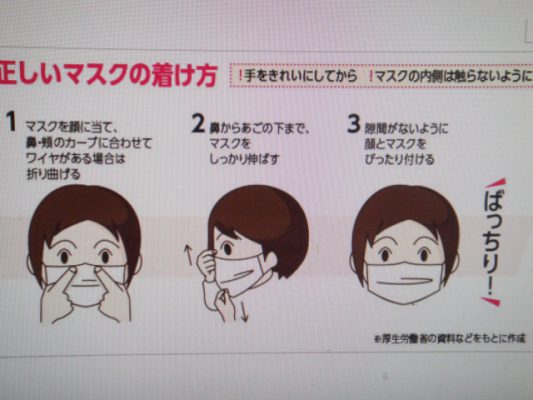



![論文が書籍化されました [01]書籍『ナイチンゲールにおける看護思想の基礎的視座』のお申込み](http://www.hocl.jp/wp-content/uploads/contents/banner07.png)
![[03]「歯がとっても大切!」健口(けんこう)生活のすすめ](http://www.hocl.jp/wp-content/uploads/contents/banner07.jpg)
![歯科衛生士の講演・講習のための資料として [03]「講習、講演に使える資料がほしい!」歯科衛生士のためのパンフレット](http://www.hocl.jp/wp-content/uploads/contents/banner05.jpg)
![印刷してすぐ使えるいろ歯かるた [04]いろ歯かるたダウンロードサービス](http://www.hocl.jp/wp-content/uploads/contents/bnr_karuta.jpg)